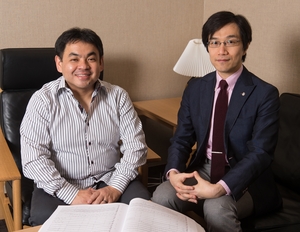 10月13日の《第552回定期演奏会》のプログラムについて、指揮者の下野竜也氏と音楽評論家の澤谷夏樹氏に語っていただきました。
10月13日の《第552回定期演奏会》のプログラムについて、指揮者の下野竜也氏と音楽評論家の澤谷夏樹氏に語っていただきました。◇ ◇ ◇
■アダムズ作品をメインとした3つの曲目
澤谷 まずは今回、ジョン・アダムズの「ハルモニーレーレ」の演奏が実現するということが、私にはショッキングでした。どのような経緯で、この作品を演奏することになったのでしょうか?
下野 プログラムは、いつも私だけで決めるのではありません。今回はシーズン全体のプログラムのバランスを見ながら、読響の事務局と一緒に考えました。その中で、4年前に読響と演奏した「ドクター・アトミック・シンフォニー」が大きな評価をい ただいたことか ら、アダムズの他の作品をやってみようかということになりました。これまで、「センチュリーロール(ピアノ協奏曲)」はイタリアのミラノ・ヴェルディ響と演奏したことがありましたし、合唱とオーケストラの「ハルモニウム」などにも興味がありました。検討する中で「ハルモニーレーレ」が良いのではとのことで、スコアを勉強し、これなら読響の定期演奏会のプログラムに相応しいと思い、決断しました。この作品は、日本で演奏されるのは、1986年の日本初演以来、約30年ぶりとのことですし。新しいものに挑戦する僕と読響、という姿を見せられるのではと思いまして。
澤谷 昨年の9月に演奏したカレル・フサ「この地球を神と崇める」も非常に刺激的でしたし、お客様も大きな期待を寄せられていると思います。プログラム全体も、「ハルモニーレーレ」のテーマである「和声」に迫るものとなっていますね。
下野 そうですね。「ハルモニーレーレ」だけでなく、今回の3つ曲の根底にずっと和声があって、プログラム全体が大きくひとつのアーチに入っているようなイメージを想像しました。フラット記号3つのハ短調で始まって、フラット記号3つの変ホ長調で終わる大きなアーチです。ソロ・ヴィオラの鈴木康浩さんとのヒンデミット「白鳥を焼く男」も以前から取り上げたいと思っていましたし、あの作品はハ長調で始まります。また、アダムズが「ハルモニーレーレ」について語った中で、ベートーヴェンを例に挙げて変ホ長調を使用したと語っていましたので、やはり最初の曲は、ベートーヴェン作品で始めたいと思いました。ハ長調のヒンデミットに繋げる作品として思いついたのが、序曲「コリオラン」でした。ハ長調やハ短調といっても、時代によってその意味合いは変わっているのだと思いますので、ベートーヴェン、ヒンデミット、アダムズのそれぞれのハ長調やハ短調がどのような意味合いを持っているのか、何かを感じて頂きたいと思いました。
■序曲「コリオラン」の衝撃
澤谷 私もこの3つの曲目を見たときに、とりわけ「コリオラン」の冒頭の響きからこの演奏会が始まることに意義深いものを感じました。あの冒頭の響きは、今の我々から見ると実に教科書通りの短調のコード進行ですが、きつい不協和音である「減七の和音」は、当時の方には相当強烈に聴こえたのではないかと思います。その1800年代初めに人々をぎょっとさせた「減七の和音」を聴かせた後、130年後や180年後にヒンデミットやアダムズはどのような刺激的な音楽を書いたのか、という流れを感じ取りました。
 下野 おっしゃる通り、あの「減七の和音」は、引き裂かれるような強さを持っていたと思います。今、私たちが演奏する時に必要なのは、作品が生まれたエネルギーの度合いを、いつも忘れてはならないで演奏することです。もちろん、当時からは想像つかないような社会になっています。飛行機で世界中を巡れるし、月にだって人類は行けるようになっています。そんな中、音についても今の時代は感覚が麻痺しつつあります。しかし、今回のベートーヴェンは、単なる「古典作品」としてとらえるのではなく、どんなに劇的なコード進行をたどり、どれほど強烈な和音を使っているのかを、感じていただきたいです。そして、演奏会全体が「ハルモニーレーレ」のように、和声について感じるきっかけになっていただければと。つまりカデンツ(和声の終結への定式)があり、常に緊張と弛緩があり、それぞれの和声のパワーや色合いを感じていただけるような機会になればと思います。
下野 おっしゃる通り、あの「減七の和音」は、引き裂かれるような強さを持っていたと思います。今、私たちが演奏する時に必要なのは、作品が生まれたエネルギーの度合いを、いつも忘れてはならないで演奏することです。もちろん、当時からは想像つかないような社会になっています。飛行機で世界中を巡れるし、月にだって人類は行けるようになっています。そんな中、音についても今の時代は感覚が麻痺しつつあります。しかし、今回のベートーヴェンは、単なる「古典作品」としてとらえるのではなく、どんなに劇的なコード進行をたどり、どれほど強烈な和音を使っているのかを、感じていただきたいです。そして、演奏会全体が「ハルモニーレーレ」のように、和声について感じるきっかけになっていただければと。つまりカデンツ(和声の終結への定式)があり、常に緊張と弛緩があり、それぞれの和声のパワーや色合いを感じていただけるような機会になればと思います。澤谷 1800年代初期、このころのベートーヴェンは、和声についていろいろ工夫していました。「プロメテウスの創造物」や交響曲第1番の冒頭などは、和声を少し逸脱します。枠の中で模索している思いがちょうど煮詰まっている時期だったと思います。その中で生まれたのが序曲「コリオラン」でのハ短調の響きだったのでしょう。これまで、調性などに頓着してこなかったお客様にも、和声について驚きを与えるような演奏会になるかもしれません。
下野 そうですね。一方で、お客様には学問的でなく、「驚き」「安定したときの喜び」「居心地の悪さ」「居心地の良さ」「劇的なもの」などを理屈ではなく感じていただき、和音の万華鏡のようなシャワーを、響きのよいサントリーホールで味わっていただきたいという思いもあります。
■ヒンデミットの音楽、冷たさと温かさ
澤谷 ベートーヴェンもヒンデミットもアダムズも、どちらかといえば和声に対してシンパシーを持つ人たちですが、それぞれに和声についての角度と勢いが違っている感じがします。とりわけヒンデミットの和声の考え方は、彼の理論書などを読むと、「斜め上の角度」を向いているように感じています。彼の理論書を読んだり、音を聴いたりしても、そんな印象なのです。「白鳥を焼く男」については、当時の一般的な和声の進行、民謡の音階を題材にした部分、そして彼の「斜め上の和声」の考え方の3つが、支点・力点・作用点となるのですが、どこか噛み合わなく違っていて、でもどこかで偶然一致したりしているような音楽に思います。その辺りから、演奏する上で捉えにくい作曲家のひとりだと思っています。そこを、鈴木さんと下野さんがどのような演奏をしてくれるのか、興味があります。
下野 ヒンデミット作品は、正指揮者に就任以来、読響と継続的に取り組んできました。「白鳥を焼く男」は、ヒンデミットの中でも有名な作品なのですが、これまで演奏してなかったので、機会を探していました。和声を巡るプログラムの中で、ヴィオラをクローズ・アップしたかったという思いもあります。ヒンデミットの講義集や著作『音楽家の基礎練習』を読むなどして、彼の音楽に感じることは、プロコフィエフなどと異なり、ことさら物事を難しくしようとしているような冷たさなのですが、一方で実にロマンティストだと思います。音楽からも優しさを秘めたものが感じられます。ヒンデミット作品を演奏するにあたって、表面にある彼の冷徹な部分を出すのか、それとも実は表面の冷たさに隠された温かな部分を出すのかによって、作品へのアプローチは随分違ってくると思います。僕は「話してみたら悪い人じゃないよ」と感じる方なので(笑)、後者です。どんな複雑なことをやっても、根底にある調性は普遍的で大きなカデンツで緊張と弛緩があるものです。「彼は表面的には冷たいけど照れ屋で、本当は違う」というような温かな部分を感じるアプローチで行きたいと思います。
澤谷 私がこれまでにヒンデミット作品の演奏を聴いて感じていた(和声法の)違いは、演奏家の方のそのようなアプローチの違いから来ていたのかも知れません。とてもハッとしました。
下野 私は残念ながらヒンデミットのオペラを演奏していませんが、彼の管弦楽曲やパロディのような作品に出会うと、「根は悪い人じゃない」と思ってしまうのです。今回の「白鳥」は、弦楽器がチェロとコントラバスだけの刈り込んだ特殊な編成なのですが、ヒンデミットの中でも聴きやすい作品だと思います。ヴィオラの特徴も味わっていただきたいです。前の曲、序曲「コリオラン」はハ短調の「ド」で暗く終わりますが、「白鳥」の冒頭のヴィオラ・ソロは、ハ長調で「ドミソ」の重音で一気に崩すように始まります。その後は、民謡風のテーマも出てきて、ヴィオラのテクニックを駆使しながら、どんどん調性も変なところに行ってしまい、「おーい、どこ行くんだ!」ってなります(笑)。でも最後は分かりやすいし、お客様にも楽しんでいただけると思います。
 ■アダムズ「ハルモニーレーレ」の楽しみ方
■アダムズ「ハルモニーレーレ」の楽しみ方澤谷 アダムズ作品で、まず私が面白いなと思ったのは、とりわけ第1楽章に顕著ですが、ミニマル・ミュージックと調性音楽は、端的に相性が良いことでした。そしてアダムズは、この作品の原理をミニマル・ミュージックとして、その素材に和声を用いているかのように感じました。
下野 (スコアを開き)何より、楽譜がとても綺麗ですよね。何を最初に鳴らしながら作曲したのか、不思議に思います。和音を鳴らして作曲したのか、細かいリズムを変化させていったのか。恐らく、両方同時にやっていたのかと思いますが。この作品こそ、感情移入せず、ドミノを並べるように書かれていますが、僕は悪い癖でつい情緒に流れてしまうので、どこかにエモーショナルものを入れてよいのかと悩むのですが、今回は最大限、彼のこのパズルを具現化できるようにしていってこそ、見える世界があるのだと思い、取り組みます。そこが、オーケストラと僕の正念場だと思います。特に第1楽章が。最後に少しだけ安息を思わす空間があるのが救いです。本当に絶妙なオーケストレーションで、光のイルミネーションを見ているような感覚になります。コンサートホールの中で、ホールの中をいろんな音を飛び回り、それを体感できる稀有な体験になることでしょう。
澤谷 ベートーヴェンの時代から今の時代まで調性に信頼を持って作曲した人たちがいて、一方でシェーンベルク以降の無調、12音技法、更に進んでトータル・セリエリズムなどに関わっていた人など、つまりアンチ調性音楽の人がいます。このアンチ調性音楽の人は、アンチ調性である故に、調性音楽が存在しなければ自分たちも存在できないという、一周回って調性音楽に信頼せざるを得ないという状況なのです。アダムズは、そのどちらでもなく、シェーンベルク以降の状況を、この作品で越えてしまったような印象を受けます。調性を相対化して使っている。
下野 そうですね。シェーンベルクという存在は、その後の作曲家にとって越えねばならない壁だったのでしょう。だからアダムズがシェーンベルクへの一つの答えとして和声学というタイトルでこの作品を書いたのだと思います。僕が興味深く思うのは、聴いていて拍子感がないという点です。僕には、この曲ではずっと実は時間が止まっているような不思議な感覚になります。
澤谷 私がこの曲から感じたことも、下野さんが「時間が止まっている」と感じられたことと共通点があるかも知れません。私はこの作品が、冒頭に顕著ですが、小節の中の音符の数が増えていき、時間というよりもエネルギーの変化の一覧表を見ているような音楽だと思いました。エネルギーが蓄積され、質量が変わっていくような。
下野 そうですね、エネルギーの蓄積。確かに普段、経験しているような音楽とは違う要素で進んでいくように感じます。自分がどこにいるのか分からなくなるような感覚です。特に第1楽章と第3楽章。そして、アダムズ作品は、先が予想もできないし、何が基軸なのか分からなくなる。機能和声的なものではないので、和声音楽的なアプローチはできません。少し第2楽章で和声的なものが匂います。この辺りは、アダムズが生理的に何かバランスを取っているように感じます。第2楽章や第3楽章に付けたタイトルについても。
澤谷 そうですね。第1楽章は「ハルモニーレーレ」というタイトルにも関わらず、和声というより和音の重なりになっている。逆にメロディアスなところは、絵に描いたような無調だったりして(笑)。この辺りも、アダムズが何か奇妙なバランスを取っているように感じます。
 下野 そして、ハ短調を思わす音が周到に散りばめられ、最後は変ホ長調が鳴り響いて終わります。音楽史において音楽は、ずっと「和声」というものに常に支配されてきました。ハイドン、ベートーヴェン、マーラーまでずっとそうでした。でもアダムズのこの作品は、それとは違います。無調のように全く出会ったことのないものに、突然出会うのではありません。どこかで会った人だけども、違う顔で出会うような驚きです。「古くて新しい、新しくて古い」感覚で、時代を超えてしまっているように思います。お客様には、とにかく生で体験していただきたい。そう、9月にワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』を聴いた方には、是非とも聴いていただきたく思います。
下野 そして、ハ短調を思わす音が周到に散りばめられ、最後は変ホ長調が鳴り響いて終わります。音楽史において音楽は、ずっと「和声」というものに常に支配されてきました。ハイドン、ベートーヴェン、マーラーまでずっとそうでした。でもアダムズのこの作品は、それとは違います。無調のように全く出会ったことのないものに、突然出会うのではありません。どこかで会った人だけども、違う顔で出会うような驚きです。「古くて新しい、新しくて古い」感覚で、時代を超えてしまっているように思います。お客様には、とにかく生で体験していただきたい。そう、9月にワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』を聴いた方には、是非とも聴いていただきたく思います。澤谷 最近は若い方がミニマル・ミュージックの演奏会を楽しむ傾向もあるので、テクノ・ミュージックなどを聴いている方にも是非とも聴いていただきたいです。一方で、ベートーヴェンやマーラーなどクラシック音楽の愛好家の方にも、興味を持って聴いていただきたいですね。どのような感想をお持ちになるか楽しみです。今回のプログラムから、三者三様の和音の推移がもたらす違いを楽しんでほしいと思います。
下野 大変有意義なお話を聴けました。本番へ向けて、さらに身が引き締まる思いです。
第552回定期演奏会
2015年10月13日〈火〉 サントリーホール
指揮=下野 竜也
ヴィオラ=鈴木 康浩(読響ソロ・ヴィオラ)
ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 作品62
ヒンデミット:「白鳥を焼く男」(ヴィオラと管弦楽)
ジョン・アダムズ:ハルモニーレーレ(和声学)
